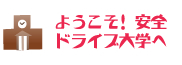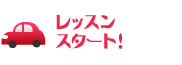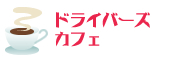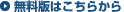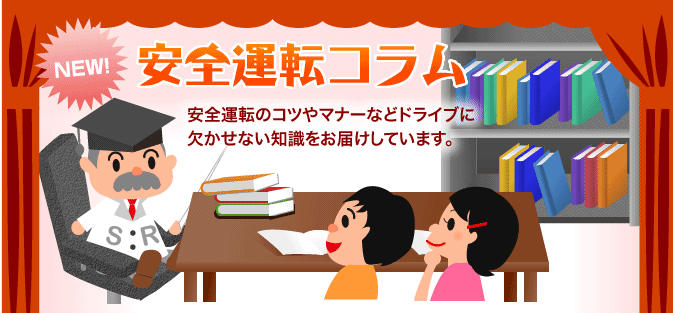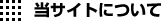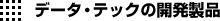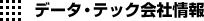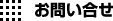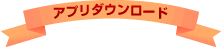


- 2026/2/1
第150回 安全運転コラム「雪道での「視界不良」が事故を招く!雪国特有の危険回避術と長距離運転の心得」掲載しました! - 2026/1/1
第149回 安全運転コラム「見えない敵「ブラックアイスバーン」!冬の始動・走行時に潜む危険と対策」掲載しました! - 2025/12/1
第148回 安全運転コラム「疲労・居眠り運転が招く年末の事故リスクと対策」掲載しました! - 2025/11/1
第147回 安全運転コラム「そのタイヤ大丈夫?雪が降る前に知っておくべき冬の準備」掲載しました! - 2025/10/1
第146回 安全運転コラム「秋の運転は「夕暮れ時」に要注意!眩しさ対策と事故を避けるための心得」掲載しました! - 2025/9/1
第145回 安全運転コラム「“ながら運転”は重大違反!スマホ使用の罰則・罰金と事故リスクを知ろう」掲載しました! - 2025/8/1
第144回 安全運転コラム「車間距離がトラブルの原因に!適切な距離の保ち方とは?」掲載しました! - 2025/7/1
第143回 安全運転コラム「真夏は50℃超えのうだるような暑さに!?炎天下の車内に放置してはいけないものと大切な命」掲載しました! - 2025/6/1
第142回 安全運転コラム「ドアパンチされた…」その時どうする?適切な対応と対策」掲載しました! - 2025/5/1
第141回 安全運転コラム「もしも交通事故の相手が無保険だったら?抑えておきたいポイントを解説」掲載しました! - 2025/4/1
第140回 安全運転コラム「もしも交通事故の相手が無保険だったら?抑えておきたいポイントを解説」掲載しました! - 2025/3/1
第139回 安全運転コラム「あなたは大丈夫?横断歩道の標識とルールをおさらい」掲載しました! - 2025/2/1
第138回 安全運転コラム「車を傷めない「雪下ろし」の方法は?」掲載しました! - 2025/1/1
第137回 安全運転コラム「雪の日の駐車に要注意!安全に停めるポイントは?」掲載しました! - 2024/12/1
第136回 安全運転コラム「EV(電気自動車)の基礎知識を解説!メリット・デメリットも」掲載しました! - 2024/11/1
第135回 安全運転コラム「11月9日は「119番の日」!緊急車両へ道を譲る際の正しい対応は?」掲載しました! - 2024/10/1
第134回 安全運転コラム「10月1日は国際高齢者デー!高齢者の運転について考えよう」掲載しました! - 2024/9/1
第133回 安全運転コラム「もし運転中に地震が起きたら?正しい対応を解説」掲載しました! - 2024/8/1
第132回 安全運転コラム「猛暑で車が故障?夏に多い車のトラブルとは」掲載しました! - 2024/7/1
第131回 安全運転コラム「交通事故の過失割合にドラレコは役立つ?」掲載しました! - 2024/6/1
第130回 安全運転コラム「集中力低下にもつながる車内の臭い...原因と対策を解説」掲載しました! - 2024/5/1
第129回 安全運転コラム「オートライト義務化についておさらい!」掲載しました! - 2024/4/1
第128回 安全運転コラム「車についた花粉はどうやって落とす?対策と予防方法を解説」掲載しました! - 2024/3/1
第127回 安全運転コラム「ガソリン代の割引も!?意外と知らない「SDカード」とは?」掲載しました! - 2024/2/1
第126回 安全運転コラム「ADAS(先進運転支援システム)とは?自動運転との違いは?」掲載しました! - 2024/1/1
第125回 安全運転コラム「雪道運転はアイスバーンに注意!スタッドレスタイヤやチェーンの準備を」掲載しました! - 2023/12/1
第124回 安全運転コラム「高速道路の走行車線と追い越し車線について再確認!やりがちな違反にも注意」掲載しました! - 2023/11/1
第123回 安全運転コラム「あおり運転を受けたらどうしたら良い?対策は?」掲載しました! - 2023/10/1
第122回 安全運転コラム「車のインロック(インキー)が起こる原因と開け方について解説」掲載しました! - 2023/9/1
第121回 安全運転コラム「レンタカーとカーシェアの違いは?どっちがお得か徹底比較!」掲載しました! - 2023/8/1
第120回 安全運転コラム「初心者マークはいつまでつける?違反したときの罰則は?」掲載しました! - 2023/7/1
第119回 安全運転コラム「内輪差と外輪差についておさらい!事故を防ぐコツは?」掲載しました! - 2023/6/1
第118回 安全運転コラム「自動運転レベルとは?気になるレベル別の現状を紹介」掲載しました! - 2023/5/1
第117回 安全運転コラム「ペーパードライバー講習とは?講習内容や料金目安などについて解説」掲載しました! - 2023/4/1
第116回 安全運転コラム「上手に車線変更するコツは?注意したいポイントも紹介」掲載しました! - 2023/3/1
第115回 安全運転コラム「車に虫が侵入!ベストな対処方法を紹介」掲載しました! - 2023/2/1
第114回 安全運転コラム「車に付いたペットの毛、どう掃除する?」掲載しました! - 2023/1/1
第113回 安全運転コラム「注意したい、おしゃれなカー用品を飾るときのポイント」掲載しました! - 2022/12/1
第112回 安全運転コラム「一瞬の油断が事故に直結!カーナビ使用時は「わき見運転」に要注意!」掲載しました! - 2022/11/1
第111回 安全運転コラム「冬を前に必見!寒い車内を今すぐ暖房で温める方法」掲載しました! - 2022/10/1
第110回 安全運転コラム「知っておきたい、車のライトの点検方法」掲載しました! - 2022/9/1
第109回 安全運転コラム「今すぐできる!車内での熱中症対策」掲載しました! - 2022/8/1
第108回 安全運転コラム「絶対にやめて!ドライブ中のポイ捨ては「法律違反」」掲載しました! - 2022/7/1
第107回 安全運転コラム「夏休みのドライブを快適に楽しむためのポイント3選」掲載しました! - 2022/6/1
第106回 安全運転コラム「6月2日は路地の日!狭い道での上手な「すれ違い」方法とは」掲載しました! - 2022/5/1
第105回 安全運転コラム「家族の安全を守るため、気を付けたい運転方法」掲載しました! - 2022/4/1
第104回 安全運転コラム「4月19日は地図の日!車で道に迷ったとき気を付けたい点」掲載しました! - 2022/3/1
第103回 安全運転コラム「お花見シーズン到来!でも、桜に見とれて事故を起こさないように」掲載しました! - 2022/2/1
第102回 安全運転コラム「春一番が吹く季節、強風による「ヒンジ」破損に気を付けて」掲載しました! - 2022/1/1
第101回 安全運転コラム「1月12日はスキーの日!車でスキー場に行く際注意すべき点」掲載しました! - 2021/12/1
第100回 安全運転コラム「エンジンがかかりにくくなる冬…やってはいけないNG行動とは?」掲載しました! - 2021/11/1
第99回 安全運転コラム「寒さが本格化する11月……運転の妨げになる霜の対策方法を紹介」掲載しました! - 2021/10/1
第98回 安全運転コラム「10月10日は釣りの日!覚えておきたい海沿いを運転する際の注意点」掲載しました! - 2021/9/1
第97回 安全運転コラム「9月2日は靴の日!覚えておきたい運転に不向きな靴」掲載しました! - 2021/8/1
第96回 安全運転コラム「8月10日は道の日!未舗装の道路を運転する際の注意点とは?」掲載しました! - 2021/7/1
第95回 安全運転コラム「夏は台風・集中豪雨が多発する季節!大雨の際は水辺の運転に要注意」掲載しました! - 2021/6/1
第94回 安全運転コラム「梅雨前の確認が大切!ワイパー交換のタイミングとそのサイン」掲載しました! - 2021/5/1
第93回 安全運転コラム「5月16日は旅の日!大人数でドライブする際の注意点」掲載しました! - 2021/4/1
第92回 安全運転コラム「4月10日は交通事故死ゼロを目指す日!死亡事故発生の主な原因とは」掲載しました! - 2021/3/1
第91回 安全運転コラム「3月19日はミュージックの日!車内で音楽を聞く際の注意点とは?」掲載しました! - 2021/2/1
第90回 安全運転コラム「新車購入者必見!把握しておきたい慣らし運転の必要性」掲載しました! - 2021/1/1
第89回 安全運転コラム「雪道の運転中は要警戒!ホワイトアウトが生じた際の対処法」掲載しました! - 2020/12/1
第88回 安全運転コラム「冬本番に向けてのフロントガラス凍結対策!活用すべきアイテムとは」掲載しました! - 2020/11/1
第87回 安全運転コラム「ウイルス対策は万全に!車内感染のリスクを軽減するための方法とは」掲載しました! - 2020/10/1
第86回 安全運転コラム「10月14日は鉄道の日!踏切事故防止のため、横断時の注意点をおさらいしておこう!」掲載しました! - 2020/9/1
第85回 安全運転コラム「台風災害が発生しやすい9月!万が一車が被害を受けたら……」掲載しました! - 2020/8/1
第84回 安全運転コラム「8月9日は駐車場の日!車を月極駐車場に止める際のポイントとは?」掲載しました! - 2020/7/1
第83回 安全運転コラム「7月1日は国民安全の日!運転時は暑さによる心理状態の悪化に要注意」掲載しました! - 2020/6/1
第82回 安全運転コラム「ジメジメとした梅雨!車をカビから守る方法とは?」掲載しました! - 2020/5/1
第81回 安全運転コラム「5月5日は薬の日!意識しなければならない服薬運転の危険性とは」掲載しました! - 2020/4/1
第80回 安全運転コラム「4月7日はタイヤゲージの日!覚えておくべき「空気圧点検」の重要性」掲載しました! - 2020/3/1
第79回 安全運転コラム「3月2日はミニの日!軽自動車を運転する際のポイントとは?」掲載しました! - 2020/2/1
第78回 安全運転コラム「寒さもピークの時期!寒冷地で運転・駐車する際の注意点とは?」掲載しました! - 2020/1/1
第77回 安全運転コラム「1月31日は生命保険の日!交通事故に巻き込まれたときに使える保険の種類」掲載しました! - 2019/12/1
第76回 安全運転コラム「1年でも屈指の交通事故発生日!クリスマスは車の運転に特に注意しよう」掲載しました! - 2019/11/1
第75回 安全運転コラム「11月11日は鏡の日!知っておきたい車のミラーにおける重要ポイント」掲載しました! - 2019/10/1
第74回 安全運転コラム「10月1日は「法の日」!意外と見落としがちな道路交通法に要注意」掲載しました! - 2019/9/1
第73回 安全運転コラム「9月11日は警察相談の日!覚えておきたい、交通事故を起こしたときの正しい行動」掲載しました! - 2019/8/1
第72回 安全運転コラム「8月1日は「水の日」!万が一車が冠水・水没してしまったときの対処法」掲載しました! - 2019/7/1
第71回 安全運転コラム「本格的な夏を迎える前に!愛車を「夏仕様」にするためのポイント」掲載しました! - 2019/6/1
第70回 安全運転コラム「梅雨に気になる車の汚れ!放置せずしっかり洗車しよう!」掲載しました! - 2019/5/1
第69回 安全運転コラム「GWは交通事故が多発する時期!考えられる原因と徹底したい対策」掲載しました! - 2019/4/1
第68回 安全運転コラム「4月2日はCO2削減の日!エコカーを運転する際のポイント」掲載しました! - 2019/3/1
第67回 安全運転コラム「多くの日本人を悩ます花粉の季節!運転時に考えられるトラブル」掲載しました! - 2019/2/1
第66回 安全運転コラム「2月9日は風の日!春の嵐に備え覚えておきたい強風時の運転方法」掲載しました! - 2019/1/1
第65回 安全運転コラム「1月10日は「110番の日」!あおり運転に遭遇したらためらわず通報しよう!」掲載しました! - 2018/12/1
第64回 安全運転コラム「慌ただしい師走、運転時は常に事故防止を意識しよう!」掲載しました! - 2018/11/1
第63回 安全運転コラム「車の死角は意外と多い!ミラー確認やバックをする際の注意点」掲載しました! - 2018/10/1
第62回 安全運転コラム「10月10日は目の愛護デー!安全運転のため知っておきたい目の特徴」掲載しました! - 2018/9/1
第61回 安全運転コラム「9月17日は敬老の日!今のうちにシルバードライバーについて知っておこう!」掲載しました! - 2018/8/1
第60回 安全運転コラム「暑さもピーク!車内で熱中症にならないための対策」掲載しました! - 2018/7/1
第59回 安全運転コラム「臭いの気になる季節、車内を快適な匂いにする方法とは?」掲載しました! - 2018/6/1
第58回 安全運転コラム「6月1日は防災用品点検の日!万が一の災害に備え徹底しておきたい対策」掲載しました! - 2018/5/1
第57回 安全運転コラム「5月は自転車月間!車を運転中は自転車に細心の注意を払おう!」掲載しました! - 2018/4/1
第56回 安全運転コラム「行楽シーズンに向けてお出かけが増える季節は、紫外線に注意しよう!」掲載しました! - 2018/3/1
第55回 安全運転コラム「交通事故発生の多い3月、安全運転を徹底しよう!」掲載しました! - 2018/2/1
第54回 安全運転コラム「2月1日は「臭いの日」!注意しておきたい排気ガスの臭い」掲載しました! - 2017/12/27
第53回 安全運転コラム「帰省などで高速道路の使用が多くなるシーズン、ETCを上手に利用しよう!」掲載しました! - 2017/12/1
第52回 安全運転コラム「12月12日は「バッテリーの日」!知っておきたいバッテリー上がりの対策」掲載しました! - 2017/11/1
第51回 安全運転コラム「事故が起こりやすい冬を前に徹底しておきたい車の点検」掲載しました! - 2017/10/1
第50回 安全運転コラム「日没が早くなる季節!意外と知らないライトの操作ガイド」掲載しました! - 2017/9/1
第49回 安全運転コラム「9月9日は「救急の日」!負傷者の救護シミュレーション」掲載しました! - 2017/8/1
第48回 安全運転コラム「帰省シーズン到来!長距離運転の心得5ヶ条」掲載しました! - 2017/7/1
第47回 安全運転コラム「夏のドライブで起こるトラブル5選とその回避方法」掲載しました! - 2017/6/1
第46回 安全運転コラム「どうやって回避する?雨の日のドライブ事故」掲載しました! - 2017/5/1
第45回 安全運転コラム「チャイルドシートは必要? 我が子を守るための「義務」とは」掲載しました! - 2017/4/1
第44回 安全運転コラム「春の取り締まり強化期間スタート!違反回避ガイド」掲載しました! - 2017/3/1
第43回 安全運転コラム「【徹底解説】ゴールド免許の条件と特典~免許別の条件比較付き~」掲載しました! - 2017/2/1
第42回 安全運転コラム「「目視」で回避する!死角に潜むキケンと事故パターン3選」掲載しました! - 2017/1/1
第41回 安全運転コラム「雪の日の走行に不慣れなドライバー必見!安全運転のポイントおさらい」掲載しました! - 2016/12/1
第40回 安全運転コラム「やっぱり気になる!スタッドレスタイヤのキホン」掲載しました! - 2016/11/1
第39回 安全運転コラム「違反切符は受けたくない!「青切符」「赤切符」の実態とリセット法」掲載しました! - 2016/10/3
第38回 安全運転コラム「行楽シーズン到来!その前にしておくべき車の日常点検」掲載しました! - 2016/9/16
第37回 安全運転コラム「紛らわしい標識が多い!? 駐停車違反にならないために」掲載しました! - 2016/8/1
第36回 安全運転コラム「子どもを車に乗せる際の注意点」掲載しました! - 2016/7/1
第35回 安全運転コラム「雨の日の運転で注意すべきこと?ハイドロプレーン現象とは??」掲載しました! - 2016/6/1
第34回 安全運転コラム「トンネル走行時の注意点~後編~」掲載しました! - 2016/4/28
第33回 安全運転コラム「トンネル走行時の注意点~前編~」掲載しました! - 2016/4/1
第32回 安全運転コラム「渋滞を安全に乗り切ろう」掲載しました! - 2016/3/1
第31回 安全運転コラム「車を賢く売るために知っておきたいポイント」掲載しました! - 2016/2/1
第30回 安全運転コラム「正しい運転姿勢を身に付けよう」掲載しました! - 2016/1/5
第29回 安全運転コラム「盗難や車上荒らしに注意!防犯対策をしよう」掲載しました! - 2015/12/2
第28回 安全運転コラム「踏切を安全に通過するには」掲載しました! - 2015/11/2
第27回 安全運転コラム「歩行者、自転車に配慮して事故を予防しよう」掲載しました! - 2015/10/1
第26回 安全運転コラム「キレイな愛車で出かけよう!洗車の仕方とコツ」掲載しました! - 2015/9/1
第25回 安全運転コラム「高速道路を安全に運転するためのポイント」掲載しました! - 2015/8/4
第24回 安全運転コラム「運転中にゲリラ豪雨に遭遇した時の対処方法」掲載しました! - 2015/7/1
第23回 安全運転コラム「飲酒運転は絶対厳禁!飲んでしまった時の対処とは」掲載しました! - 2015/6/10
第22回 安全運転コラム「自動車保険に上手に加入するコツ」掲載しました! - 2015/5/1
第21回 安全運転コラム「ドライブレコーダーを活用しよう」掲載しました! - 2015/4/1
第20回 安全運転コラム「事故を起こした時にやるべきこととは」掲載しました! - 2015/3/2
第19回 安全運転コラム「ペーパードライバー脱出!運転が上達するコツ」掲載しました! - 2015/2/2
第18回 安全運転コラム「運転中に災害が発生したときの対策」掲載しました! - 2015/1/6
第17回 安全運転コラム「車酔いの原因と対策」掲載しました! - 2014/12/1
第16回 安全運転コラム「これで安心!タイヤチェーンの装着方法」掲載しました! - 2014/11/4
第15回 安全運転コラム「覚えておきたい夜間運転のポイント」掲載しました! - 2014/10/1
第14回 安全運転コラム「坂道・山道運転のコツ」掲載しました! - 2014/9/1
第13回 安全運転コラム「運転マナーを身につけよう」掲載しました! - 2014/8/1
第12回 安全運転コラム「長距離ドライブを楽にするコツ」掲載しました! - 2014/7/1
第11回 安全運転コラム「夏目前!ドライブにおける暑さ対策」掲載しました! - 2014/6/2
第10回 安全運転コラム「雨の日の運転テクニック」掲載しました! - 2014/4/28
第9回 安全運転コラム「運転時の眠気と疲れをいやすリフレッシュ方法」掲載しました! - 2014/4/1
第8回 安全運転コラム「4月から始めよう!環境とお財布にやさしいエコドライブ」掲載しました! - 2014/3/4
第7回 安全運転コラム「レンタカー&カーシェアリング利用のすすめ」掲載しました! - 2014/2/3
第6回 安全運転コラム「運転が怖くなくなる、初心者のための5つの心得」掲載しました! - 2014/1/6
第5回 安全運転コラム「雪道を安全に走るためには、事前の準備が大切!」掲載しました! - 2013/12/6
第4回 安全運転コラム「データ・テックの道路交通安全方針をご紹介します!」掲載しました! - 2013/10/1
第3回 安全運転コラム「10月の景色といえば・・・免許証のあのカラー!」掲載しました! - 2013/9/2
第2回 安全運転コラム「おじいちゃんやおばあちゃんに会いに行こう!」掲載しました! - 2013/8/1
新コンテンツ「安全運転コラム」連載開始しました! - 2013/4/5
前回キャンペーン「ドライブで見つけた絶景スポット」結果発表! - 2013/2/26
【レッスン8】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第7回を公開しました! - 2013/2/26
前回キャンペーン「思わずにっこり!誰かの運転マナー&親切」結果発表! - 2013/2/1
新プレゼントキャンペーンスタート!「ドライブで見つけた絶景スポット」 - 2012/12/28
前回キャンペーン「こんなドライブデートがしたい!」結果発表! - 2012/12/25
【レッスン7】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第6回を公開しました! - 2012/11/30
新プレゼントキャンペーンスタート!「思わずにっこり!誰かの運転マナー&親切」 - 2012/11/30
【レッスン6】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第5回を公開しました! - 2012/10/30
前回キャンペーン「若葉マークの思い出」結果発表! - 2012/10/30
【レッスン5】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第4回を公開しました! - 2012/10/26
新プレゼントキャンペーンスタート!「こんなドライブデートがしたい!」 - 2012/9/14
前回キャンペーン「渋滞を乗り切るとっておきのコツ★」皆様のつぶやきをご紹介! - 2012/8/17
新プレゼントキャンペーンスタート!「若葉マークの思い出」 - 2012/8/8
【レッスン4】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第3回を公開しました! - 2012/7/26
前回キャンペーン「サービスエリアで食べた!&食べた~い!グルメ」皆様のつぶやきをご紹介! - 2012/6/25
【レッスン3】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツ第2回を公開しました! - 2012/6/18
新プレゼントキャンペーンスタート!「渋滞を乗り切るとっておきのコツ★」 - 2012/5/17
【レッスン2】安全運転とSafety Recにおける 得点アップのコツを公開しました! - 2012/5/2
新東名高速開通記念!新プレゼントキャンペーンスタート! - 2012/5/2
ドライブファンなびにて前回キャンペーン「運転中に起こった珍事件」への投稿をご紹介しています。 - 2012/4/1
「安全運転ドライブ大学」サイトが公式オープン!プレゼントキャンペーン開催中。ぜひご応募下さい。 - 2012/3/12
運転診断スマートフォンアプリ『SefetyRec』プロデュースの「安全運転ドライブ大学」サイトがプレオープン!

雪道での「視界不良」が事故を招く!
雪国特有の危険回避術と長距離運転の心得

2月は積雪や吹雪が厳しくなり、連休の観光などで長距離運転が増える季節です。雪道に不慣れなドライバーにとっては、視界不良や路面凍結、疲労の蓄積といった危険が重なります。
とくに雪による視界不良は距離感や車線の把握を難しくし、判断ミスから重大事故につながる恐れがあります。
本記事では、ホワイトアウト時の対処法や疲労・眠気対策など、冬の安全運転に欠かせないポイントを分かりやすく解説します。
 雪が視界にもたらす危険
雪が視界にもたらす危険

雪道で運転を行う際、もっとも警戒すべきは「視界の悪化」です。とくに2月は、激しい吹雪で周囲が真っ白になり、方向感覚や地形の起伏がわからなくなる「ホワイトアウト」が発生しやすくなります。
ホワイトアウトの状態では、前走車のテールランプすら見えなくなり、先行車との距離感や車線の位置が把握できなくなります。また、雪が降っていなくても、路面の雪が風で舞い上がる「地吹雪(じふぶき)」にも注意が必要です。万が一、視界が遮られた際は、ハザードランプを点灯して自車の存在を周囲に知らせてください。無理に進むのではなく、安全な場所に停車して天候の回復を待つ勇気を持ちましょう。
 雪道での「急」のつく操作が危険な理由
雪道での「急」のつく操作が危険な理由

雪道や凍結路面は、乾燥したアスファルトに比べてタイヤのグリップ力が極端に低下します。そのため、「急ブレーキ」「急ハンドル」「急加速」といった操作は、即座にスリップやスピンに直結します。
例えば、急ハンドルを切ると、遠心力によってタイヤが横滑りを始め、コントロール不能に陥ります。また、急加速は駆動輪の空転を招き、発進すら困難にさせます。雪道ではすべての操作を「ゆっくり、じんわり」と行うことが鉄則です。常に路面状況を予測し、余裕を持った動作を心がけることが、不測の交通事故を防ぐ鍵となります。
 長距離運転における疲労蓄積のメカニズムと
長距離運転における疲労蓄積のメカニズムと
休憩の取り方

冬の長距離運転は、眠気・疲労への対策も欠かせません。雪道の運転は、刻々と変わる路面状況や視界不良に対応するため、通常の道路よりも脳や神経を激しく消耗します。そのため、いつも以上に注意が必要です。 ★対策として、以下の休憩ルールを徹底しましょう!
とくに、一面の銀世界を走り続けると、景色の変化の少なさから「ハイウェイ・ヒプノーシス(高速道路催眠現象)」に陥りやすくなり、無意識のうちに注意力が散漫に。疲労が蓄積すると反応速度が鈍り、居眠り運転のリスクも高まります。
 加えて、冬の車内は暖房の効き過ぎで空気がこもりやすく、頭がぼんやりしがちです。定期的に窓を開けて冷たい外気を取り入れ、脳をリフレッシュさせましょう。同乗者がいる場合は積極的に会話を楽しみ、一人の場合はラジオや音楽で聴覚を刺激するのも有効です。
加えて、冬の車内は暖房の効き過ぎで空気がこもりやすく、頭がぼんやりしがちです。定期的に窓を開けて冷たい外気を取り入れ、脳をリフレッシュさせましょう。同乗者がいる場合は積極的に会話を楽しみ、一人の場合はラジオや音楽で聴覚を刺激するのも有効です。
また、到着時間を気にし過ぎると焦りから精神的疲労が増すため、「あそこのサービスエリア(もしくはパーキングエリア)を目的地にしよう!」といった、段階的なスケジュールを組むことが、心の余裕を生みます。
| 2時間に1回、20分程度の休憩を! | 車外に出て新鮮な空気を吸い、ストレッチをしましょう。 |
| 15分程度の仮眠で事故を防止! | 強い眠気を感じたら無理をせず、安全な場所で短時間の仮眠を取るのも効果的です。 |
| カフェインやガムを上手に活用! | 一時的な眠気覚ましにはカフェインやガムが有効!しかし、過信は禁物です。「眠いな」「疲れたな」と感じたら仮眠や休憩を! |
 雪道走行時のブレーキと車間距離の重要性
雪道走行時のブレーキと車間距離の重要性

雪道での制動距離(ブレーキを踏んでから止まるまでの距離)は、乾燥路面に比べて数倍から、路面状況やタイヤの状態によっては10倍以上にまで伸びる場合があります。そのため、雪道を運転する際は「車間距離の確保」は非常に重要です。
前の車が急停止しても安全に停まれるよう、普段の2倍〜3倍以上の車間距離を常にキープしましょう。ブレーキをかける際は、まずはアクセルを離してエンジンブレーキをきかせ、徐々にフットブレーキを優しく踏み込みます。
最近の車にはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が搭載されていますが、ABSは「滑らないための装置」ではなく「滑っている間もハンドル操作を可能にするための装置」です。過信せず、余裕を持った速度管理を徹底してください。
 いかがでしたか。冬の雪道運転は、「見えない・止まれない・曲がれない」リスクを常に意識することが大切です。視界不良や路面状況を甘く見ず、十分な車間距離とこまめな休憩を心がけましょう。 無理をしない判断と余裕ある運転が、冬の事故防止につながります。
いかがでしたか。冬の雪道運転は、「見えない・止まれない・曲がれない」リスクを常に意識することが大切です。視界不良や路面状況を甘く見ず、十分な車間距離とこまめな休憩を心がけましょう。 無理をしない判断と余裕ある運転が、冬の事故防止につながります。